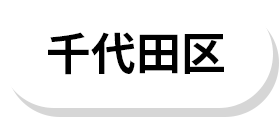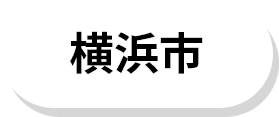オフィスでは、照明や空調はもちろん、パソコンや複合機、シュレッダーや電子レンジなど、さまざまな電子機器が使用されています。
電力が不足してしまうと、日々の業務の遂行に支障をきたし、経済的な損失にもつながりかねないため、適切な電気容量の確保は必須です。
今回は、オフィスの電気容量について解説します。
オフィスに必要とされる電気容量の目安
オフィスに必要な電気容量は、1人あたり6A(アンペア)が目安といわれています。
この数字は、5名程度の小規模なオフィスでの電気容量(30~40A)が基準となっており、1フロアに勤務する従業員数が多くなるほど、必要なアンペア数も増える計算です。
オフィスでの主な電気機器の消費アンペア数は、以下が目安となります。
- 空調(エアコン1台)8~12A
- 照明(蛍光灯1本)0.3~0.4A ※LED照明の場合、大幅な省エネ効果が期待できる
- ノートパソコン 0.5~1A
- デスクトップパソコン 2~4A
- 複合機 12~20A
- シュレッダー 3~6A
- 電子レンジ 6~15A
- 電気ポット 9~13A
オフィスで使用する具体的な電気容量は、毎月電力会社から発行される使用明細にて確認することができます。
しかし移転となると新しいオフィスの設備や機器の種類、稼働時間や使用状況によっても変動するため、契約アンペア数は余裕を持たせておく必要があります。
オフィスの契約アンペアの確認方法
電気の容量(契約アンペア数)は、内見や内覧時に分電盤のブレーカーに記載された数字で確認することが可能です。
スマートメーター(ブレーカー機能内蔵の次世代型の電気メーター)で契約アンペアが設定されている場合は、アンペア数の記載がないため、管理会社や貸主に問い合わせましょう。
分電盤には供給された電気を分配する機能があり、複数の回路に分岐されています。
そのため、オフィスレイアウトの際は、それぞれの回路につながる電子機器類が許容電流を超えないように回路設計する必要があります。
電気容量が不足する際の対処方法
電気容量が足りない場合の対処法の一つに、契約アンペア数の引き上げがあります。
至ってシンプルな解決策に見えますが、ビル全体の電気の総量は決まっており、フロア面積による割り当ての都合などもあるため、必ずしも実施できるとは限りません。
アンペア数の変更が可能であっても、ケーブルやブレーカーの交換などで大規模な工事が必要となることあるため、まずは管理会社や貸主に確認を取りましょう。
退去時には原状回復(元のアンペアに戻す)義務が発生する点にも注意が必要です。
また、分電盤に空き回路があれば、配線工事を行うことで容量不足が解決できることもありますが、これらの対処法が取れなければ、移転も視野に入れなくてはなりません。
電気はオフィスの生命線
電気は企業活動の生命線であり、オフィスの規模に合った電気容量の確保は不可欠です。
電圧・電源・回路・配線などの専門性が付随する分野でもあるため、少しでも不明・不安な点があれば、専門業者や専門家に相談することをおすすめします。